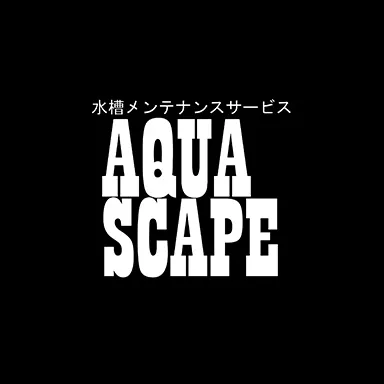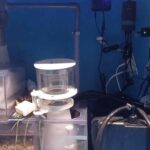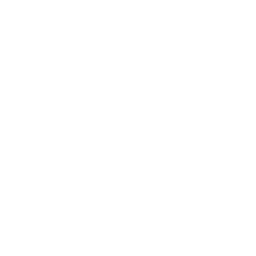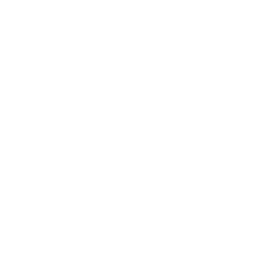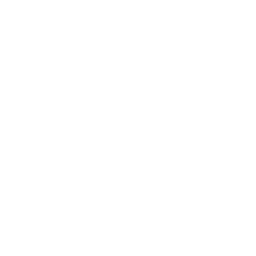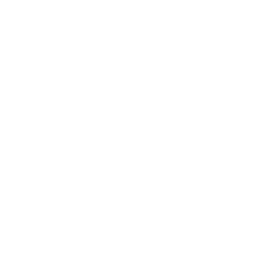魚の学名ってなに??

魚そのものを紹介する記事の中で”学名”って使ってるけど、学名とは何か?
学名というのは世界共通の名前です。学術上必要なので付けられてます。
例えば海外の学者にウナギと言っても分かりませんよね?なので「Anguilla japonica」といった学名で世界中の学者と会話をするんです。
この学名、見てるとすごい馴染みのない英単語だと思いませんか??それもそのはず、英語じゃないんですね。英語だったら”英名”というのがありますんで。
では「学名とは何語か?」というと、これはラテン語になります。
「ラテン語ってどこの言語?」まで言うと、イタリアのローマ帝国を起源とした言語で、ヨーロッパの言語の元になったと言われてますね。
じゃあ「なぜラテン語を使うのか?」ってとこですが、これは18世紀にスウェーデンの学者のリンネが「世界共通の呼び名が必要だよね~」ってことでラテン語を使った分類法を作ったことに起源するみたいです。
当時こういった生物の研究が盛んだったヨーロッパで、しかもヨーロッパ言語の元になったと言われるラテン語であれば各国の学者もとっつきやすいということでラテン語が採用され、それが今に受け継がれているということでしょう。
もし当時世界的にも生物学が盛んな地域が日本だったのなら、学名は日本語だったのかもしれませんね~
それと、ラテン語が今はほぼ使われなくなった言語というのも学名として採用しやすかったのかもしれませんね。もし学名を世界共通語、今であれば英語を使っていたとすると…世界共通語ってのは世界情勢によって変わります。英語じゃなくて日本語が共通言語になる時代だって来るかもしれません。そうなるとその都度学名も変えないといけなくなります。それよりはもう使わないラテン語だからこそ、未来の情勢が変化してもそのまま使いやすいのかもしれません。
この学名、名付け方にもルールが存在していて、【二名法】や【三名法】があります。
簡単に二名法だけ触れると、学名を「属の名」と「種の名前」に分けて記載するものです。
↑のウナギ(正確には二ホンウナギ)だとAnguillaが属名=ウナギ属でjaponicaが種の名前=ニホンウナギですね!