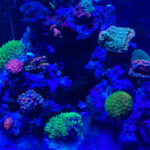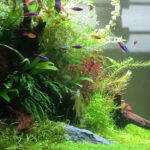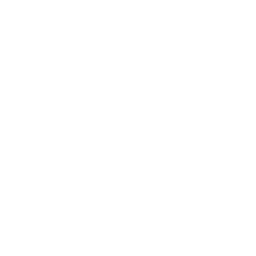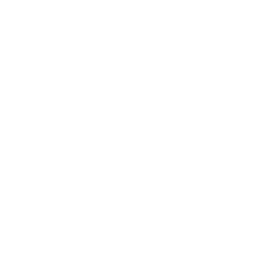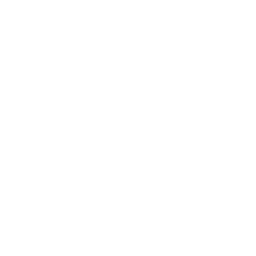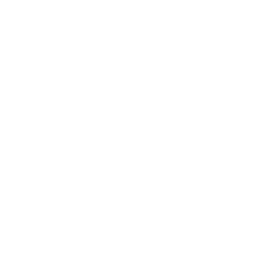分類の話
生き物について調べていると目にすることがある『綱』『目』『属』とかの文字。
特に意識しない言葉ですがこの仕事をしてると目にすることが多いもんで…気になったので調べてみました。
分類学における定義
まずこの見慣れない漢字で分けられてる項目、主に全部で7段階に分かれてまして
界→門→綱→目→科→属→種
この順番で分かれてます。
どういう基準で分けているかというと、共通点や相違点で分類を分けているようです。
例えば最初の分類にあたる『界』であれば【動物or植物】ってことですごーく大きな分類で二分してたり、後ろの方の分類の『科』だったら【イヌorネコ】のように『界』よりは共通点が限定的になったり相違点が増えてくることで細かな分類に分かれていきます。
でもこの『界~~~種』に至る7つの分類の仕方も『国際動物命名規約』や『国際原核生物命名規約』など機関・組織によって呼び方が変わったりと世界的に統一されているかってところも言いにくいものみたいですね。。
『界』も【動物or植物】だけの『二界説』が最近では『五界説』まで分かれてたり
『科』の分類について「こういう相違点があったら科の分類にする」とかの定義があるわけでもないみたい…
いちおう「起源や祖先が同じものは同じグループに分ける」って決まりはあるみたいですが…
けっこう今でも議論されてる分野みたいですね。
この7つの分類の更に上位、『界』の上に『ドメイン』って階層も言われてるみたいですね。
バクテリア(真正細菌)、アーキア(古細菌)、真核生物って3つの分類があるみたいです。
微生物の世界の分類みたいですね~~、もうキリが無さそうですが…汗
分類の事例~人間はどんな分類?
例えば人間であれば
動物界→脊索動物門→哺乳綱→霊長目→ヒト科→ヒト属→ヒト種(ホモサピエンス種)
だそうです。
ちなみにヒト科はオランウータンとかもそうらしいです。
『科』までの分類上ならオランウータンも人間も一緒みたいです 驚
ちなみに、【哺乳類】とか【霊長類】とかよく聞きますが
これ見てると『類』って分類無いんですよね…分類学上は『類』ってランクは無いみたいです…
なんで「哺乳類→哺乳綱」だし、「霊長類最強→霊長目最強」が正しいみたいですよ~~
他の分類の生き物も紹介すると、
魚類
動物界→脊索動物門→硬骨魚綱~
両生類
動物界→脊索動物門→両生綱~
カニ
動物界→節足動物門~
エビ
動物界→節足動物門→甲殻亜門→軟甲綱→十脚目~
昆虫
動物界→節足動物門→六脚亜門~
ウニ
動物界→棘皮動物門~
貝類
動物界→軟体動物門~
サンゴ
動物界→刺胞動物門→花虫綱→八放(六放)亜門~
クラゲ
動物界→刺胞動物門~
こんな感じ。こうやって見ると
まず脊椎動物かどうかで早い段階で大きく分かれていたり
虫とエビが近い仲間とか言われるのは節足動物門って分類で一緒だからだったり(なので門ってランクで分かれてるから近い仲間といってもだいぶ違うよな~って思ったり笑)
サンゴとクラゲは近い存在って言うのもなんとな~くわかりますね。
ちなみに『亜綱』とか新しい分類が出てますが、これは
例えば『綱』と『目』の間の分類って感じみたいです。
『綱』のランクで分けるにはもっと細かくなるけど、『目』にするほど細かく分けるほどでもない、って感じで『亜』をつけるようですね。
この分類で分けられない意外な存在~ウイルス
こんだけいろんな段階で分けてるんだから、あらゆる生き物がこれに属するんじゃないかと思うでしょう。
『ドメイン』って8分類階級まで使ったら細菌まで分けちゃってるんだから。
でも我々がよく聞く”生き物”と思われる存在の中で、この分類階級のどこにも属さない、分類学の外に存在するものがいるんです…!!
それが『ウイルス』。
コイツは今でも生物かどうか議論されている存在で、今のところ『ウイルスは生物ではない』という結論になっているようです。
ウイルスと細菌って病気の原因になるものだから、なんか一括りというか同じ存在というか…そんな認識じゃないでしょうか??
実はウイルスと細菌は大きく違う存在なんですよね。
ここの違いの定義ってのが【細胞構造を持つかどうか】だったり【自己増殖ができるかどうか】だそうです。
細胞構造ってのは細胞膜や細胞壁があるかどうか、って話ですね。細菌にはコレがあります。
そして細菌ってのは自己増殖ができます。人間の細胞とかと同じ、自分で増えることができます。
でもウイルスってのは自己増殖できないんですね。どうやって増えるかというと、
細胞に寄生して増えるんですね。
細胞が増えるときってDNAやRNAってのを複製して増えるんですが、ウイルスはそれができない…
なので細胞に寄生して、その細胞に自分のDNA(orRNA)を増やしてもらうことで増殖します。
細胞が持ってる設備を間借り(というか強奪?)して増えるんです。恐ろしいヤツです。。
※DNAとRNAの違いとか増殖のプロセスは筆者の専門ではないので間違ってるかも…ご容赦ください汗
こういった定義からウイルスと細菌ってのはだいぶ違う存在だそうです。
【後書き的な…調べた理由】
以上、分類学の話でした。なぜこんなこと調べたかというと
魚の病気について勉強していた結果、この辺の分野に辿り着きました。
分類ってのがどんな特徴を基に分けられているのか、それによって共通して発生しやすい病気があったりその治療法があるんじゃないか?と思ったのが始まりです。
もちろん魚種の特定とか生活の特徴とかを知るために分類分けに興味を持った面もありますけどね。
そして魚の病気にもウイルス性のものと細菌性のものがあります。
魚の病気は特定が難しく、対処法も病原菌によって変わるものでアクアリストにおいては非常に難儀する問題です。
その対処法の共通性が見つかればいいのだが…と思って勉強していたら『門』だの『綱』だの出てきたので、まとめてみました。
けっこう難しい話だし、直接役に立ちそうな情報がある記事ではないですが…
ひとつ豆知識として覚えていただければ幸いです!