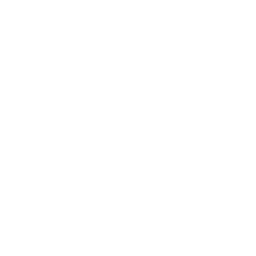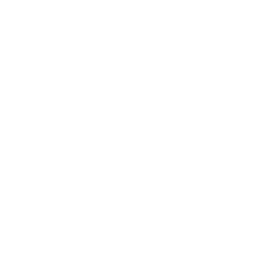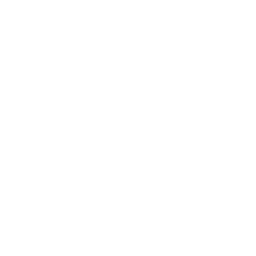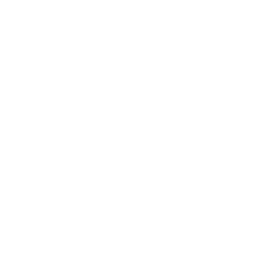水槽の本質!!バクテリアの種類
こんにちは!今回も閲覧ありがとうございます。
愛媛を中心に水槽メンテナンス業者をやってます、AQUASCAPEです。
今回は何度もワードは出てきている【バクテリア】についての大まかな分類の話です。
これまでにバクテリアの話をしたときに『好気性』とか『嫌気性』とかのワードが出てきてましたが、これについてもっと詳しく触れていきましょう。
好気性細菌(バクテリア)
これは酸素が多い環境で活動するバクテリアです。
アンモニアや亜硝酸を分解してくれるバクテリアたちがコレでして、硝化細菌とも言いますね。
NH₃→NO₂→NO₃
という順に分解していきますが、この記号を見るとだんだん酸素”O”が増えていってます。なので『酸化』とも言います。
酸素が多い環境で分解をしていく過程で”酸化”することで成分が変化していきます。
ちなみにですが、アンモニアNH₃を亜硝酸NO₂に分解するバクテリアと
亜硝酸NO₂を硝酸塩NO₃に分解するバクテリアは別種みたいです。
ひとくちに好気性バクテリアや硝化細菌と言われてますがこれは総称で、それぞれ別種のバクテリアが水槽内に共存してるんですね~
好気性細菌でも有名で役立つのは『バチルス菌』があります。
この菌は厄介なビブリオ菌を倒したりデトリタスを分解するチカラがあります!覚えておいて損はない
「デトリタスってもう分解しきれない物質じゃないの?」と筆者も長らく思っていましたが、ちゃんと分解する能力がありました!
正確にはデトリタスを細かくして、他のバクテリアが使いやすい状態まで変化させてくれるってことなんですが、難しい話なので今回は割愛で…
嫌気性細菌(嫌気性バクテリア)
好気性とは反対で、酸素が無い環境で活動するバクテリアです。
酸素の無い環境でどう活動しているのか?ってところですが、
NO₃→NO₂→N₂
という形に分解してくれます。これを『還元』って言います。この活動をしてくれる菌を脱窒菌とも言いますね。
これを見ると好気性とは逆に酸素”O”が無くなっていってますよね?
嫌気性細菌はここで酸素を回収することで活動しているようです!
酸素に触れるのは嫌がるけど、生きるために酸素は必要…難しいヤツです…
ただ素直にNO₃を窒素ガスに分解するだけじゃなくて、そのときに硫化水素も生み出しちゃうようですが…水槽の砂が黒くなってるのを経験したことある方もいると思いますが、アレが硫化水素でして。それの発生原因がこの脱窒菌=嫌気性細菌の仕業なんですね。
嫌気性細菌は硝酸塩を減らすのに役立ちますので、サンゴ水槽では意図的に嫌気層を作ることもよくあります。
名前の通り酸素に触れるとダメなので、通水性を良くし過ぎると嫌気性細菌がいなくなってしまいます…
通性嫌気性細菌(嫌気性バクテリア)
嫌気性細菌にも もう一種類ありまして、
この通性嫌気性細菌は酸素がある環境でも無い環境でも活動できる細菌でして、酸素の有リ無シで性質が変わるんです…!
代表例にポリリン酸蓄積細菌ってのがいまして
・酸素がある環境→リン酸塩PO₄を取り込んで活動する
・酸素がない環境→リン酸塩PO₄を放出してポリリン酸を使って活動する
という性質があります。このポリリン酸蓄積細菌にリン酸塩を抱えさせたままプロテインスキマーで水槽から取り除くことでリン酸塩を下げることができます!!
↑の好気性細菌のところでバチルス菌について話しましたが、通性嫌気性細菌のバチルス菌もいるようですよ。
【まとめ】
バクテリアにも大きく3つの環境菌がいて
- 好気性細菌~酸素があるとこで活動
- 嫌気性細菌~酸素がないとこで活動
- 通性嫌気性細菌~両方で活動できるが性質が変わる
そしてどの種類も水槽の環境維持には重要になる!
好気性がNH₃、NO₂をNO₃まで分解し
嫌気性がNO₃、PO₄を還元する
これらのバクテリアを使いこなすことで良い水景を維持できるわけです!
目に見えないのでわかりにくいですが、自分の水槽にどの種類のバクテリアがどのくらいいるのかを想像しながら調整していきましょう。
その目安を教えてくれるのが定期的な水質検査。変化率を見ることでどの種類のバクテリアがどれだけ活動しているのかを推察してメンテナンスしていくことです!