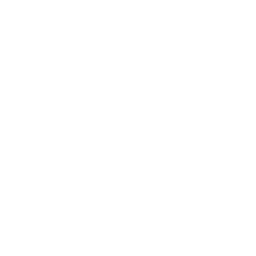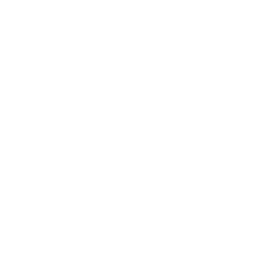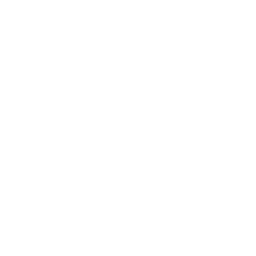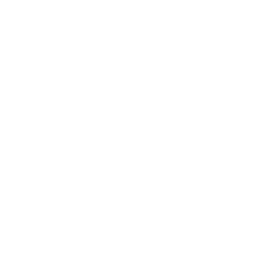海水魚の病気一覧
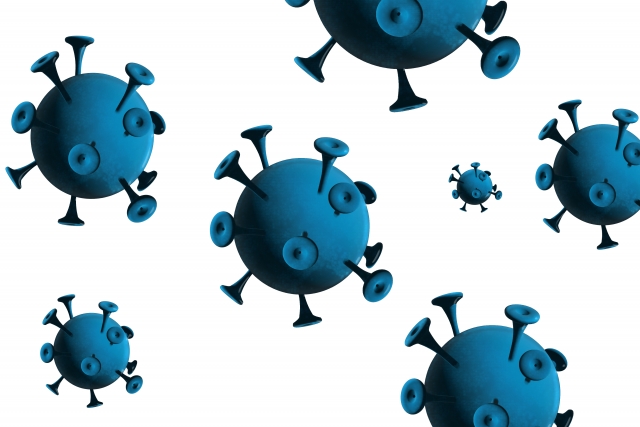
こんにちは、愛媛で水槽メンテナンスサービスをしているAQUASCAPEです。
海水魚水槽をしているとどうしても経験することがある魚の病気について、話していきます!
海水魚の病気は一見似ている症状なのに対処法が違うなど、判断が難しいです…
これは知識と経験で判別できるようになるしかないですが、今回の記事を見てその一助になれば幸いです!
病気の原因には『ウイルス』『細菌』『寄生虫』の3つに大別できます。
この原因種別によって特徴が共通していたりしますので、意外と大事なポイントです!
【病気 早見表】
| 病名 | 原因種別 | 症状 | 対処法 |
| 白点病 | 寄生虫 | 白い粉が付く。魚が弱る。 | 薬浴 |
| ウーディニウム | 寄生虫 | 白点に似てるが粉が細かく、うっすら黄色っぽい。致死率高い。 | 薬浴 |
| トリコディナ | 寄生虫 | 白っぽい膜に覆われる。致死率高い。 | 淡水浴 |
| リムフォシスティス | ウイルス | 初期は白点病っぽいが菌が大きくなる。カリフラワー病とも。 | 物理除去(淡水浴、薬浴) |
| ハダムシ | 寄生虫 | 透明で気づきにくい。魚が弱る。 | 淡水浴 |
| ビブリオ菌感染症 | 細菌 | 出血したように体が赤くなる。致死率高い。気づいた時には手遅れのことが多い。 | 薬浴 |
白点病
こちらは別記事でも触れてますが、最もポピュラーな病気なので再度紹介。
寄生虫による病気で、繊毛虫という部類の寄生によって起こる病気です。
魚の体表に寄生して養分を奪っていくので魚が弱ってしまいます。
白点病自体の致死率は低い印象ですが、きっちり対処しないとずっとこの病気に悩まされてしまします…
この病原虫には『寄生~繁殖~産卵』のサイクルがあるのですが、水中を漂っている期間に薬浴して対処するのが効果的です。
そのため対処法は薬浴と水換えで白点虫を根絶する作業になります。
薬は銅イオンやグリーンFゴールド顆粒(以降GFGと略します)、エルバージュがいいです。
なお、白点虫は自然界にもごく普通に存在するのですが、野生の魚はほとんどこの病気にはかからないと言われてます。…が、罹った魚を目にすることが無いからそう言われてるだけじゃないかな…?養殖生簀の魚はよく白点病になってるそうです。
ウーディニウム病
こちらも寄生虫による病気で、渦鞭毛虫の寄生が原因。
白点病に似ていますが、粉の粒がより細かく、色がうっすら黄色っぽいのがこの病気の見極めポイント。
そして病気の進行が早く、致死率も高いです。
こちらも白点病同様、薬浴にて対処しましょう。
銅イオンが一番強力で、次にエルバージュ、そしてGFGの順に薬の強さが変わります。
銅は強力で万能なんですが、その分生体への負担も大きいです。魚の状態を見てどの薬を使うか判断してみてください。
トリコディナ病
これも寄生虫による病気。白点病と同じ系列の繊毛虫による寄生になります。
特にクマノミにかかりやすく、病気の進行が早くて致死率も高いです。
体表が白い半透明の膜のようなもので覆われてきます。
早期発見であれば淡水浴を何日か繰り返して治癒できることがあるようです。
そして淡水浴後にGFGで薬浴もしてあげると、粘膜保護の役割も果たすのでなお良いとのこと。
リムフォシスティス(リンホシスチス)病
こちらはウイルスが原因による病気。
初期症状は白点病っぽいんですが、その白点がだんだん大きくなってくるので白点とは別だと気付けます。
それが大きくなると魚の目のような塊になってきます。その状態がカリフラワーのようなんでカリフラワー病とも呼ばれてます。
見た目の割に致死率は低いんですが、口周りに発症すると上手くエサが食べられなくなるので要注意。そして何より見栄えが悪いです…
対処としては淡水浴したあとにリムフォで大きくなったものをピンセットなどで物理的に除去、その後傷口の消毒として薬浴してあげるのが効果的とされているようです。
ただ、ウイルス性の病気については具体的な予防や治療法は確立されてないようです…なので淡水浴や薬浴が治療になるとは言い難いようで。予防についてはウイルスを除去ってことで殺菌灯は効果的かと思いますが。
養殖業界ではウイルス性の病原体についてはオゾン処理や紫外線でウイルスのDNA・RNAを破壊することで殺菌する方法が予防に使われているようです。それとヨウ素消毒も有効とされているようです。ヨウ素はアクアリウム業界でもいくつか製品が流通しているので、もしかするとウイルス性の病気であるリムフォシスティスにもヨウ素が一定の効果があるかもしれません。。。
ハダムシ
こちらは寄生虫による病気です。
今までの寄生虫と違って大きいです。(大型寄生虫病)
魚に寄生しているときは透明でわかりにくいのですが、よーく見ると体表に小さな凸部分があったりして目視で確認できることもあります。
これも魚から栄養を吸ってるのでだんだん魚が弱ってきてしまいます。
でも対処は一番カンタン。淡水浴で一発です!
淡水浴した後の容器を見ると半透明の米粒のようなものが落ちてます、これがハダムシ。死ぬと透明から半透明になってわかりやすくなります。
水槽内で繁殖されちゃうと何日も継続して根絶してやらないといけないので大変ですが、軽度であれば一回で解決できる病気ですね。
このハダムシ、アクアリウムは勿論ですが養殖生簀でよく発生するので業者さんを悩ませる存在だそうです。
ビブリオ菌感染症
これは細菌性の病気。ビブリオ菌と言ってますが一種類ではなく、ビブリオ属系統の細菌が起こす病気の総称です。人間でも腸炎ビブリオやコレラ菌って病原菌ありますが、これもビブリオ菌です。
通性嫌気性菌って言って、主に酸素が少ないとこで生息する最近です。自然界でも水槽の中でも必ず存在する常在菌です。なので通常通りの免疫力があれば感染はしないんです。
実は分解者の一面もあり、ライブロックのキュアリングに役立つ存在だったりするんですが、免疫が弱った生体には容赦ない存在になります…
症状としては体が内出血したように赤くなるのが一番わかりやすい症例です。
進行すると敗血症の症状が出たり、ビブリオ菌が魚の細胞を生きたまま分解し始めたりと…恐ろしい病状を呈するようです…
対処は薬浴が効果的。早期発見できないと手遅れの場合が多く、治療まで根気よく薬浴を続けないと難しいです。
【まとめ~ 一番は病気が発生しない環境づくり】
以上、よく聞く海水魚の病気でした。
治療の方法も紹介はしましたが、水槽内の魚を捕まえて薬浴するのはなかなか大変です…よく岩の陰に逃げちゃうもんで…
病気の対処で一番の方法は【病気が発生しない環境を創ること】
殺菌灯の導入や、病気の温床になるデトリタス(=汚れ、澱み)が溜まりにくい水流作りやメンテナンスが重要です。